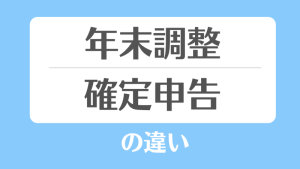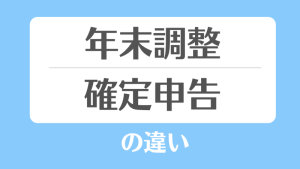「青色申告」と「白色申告」の違いとメリット・デメリットは、
「手間と節税効果」で区別します。
| 比較項目 | 青色申告 (最大65万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
| 節税効果 | 最大65万円控除+赤字繰越・事業専従者給与など多彩な優遇措置あり | 控除は10万円だが、多少の節税は可能 | 控除なし・節税効果はほぼなし |
| 手続きの手間 | 多い (複式簿記・帳簿保存・申請書提出・e-Tax必須など) | やや多い (簡易簿記・一部帳簿・申請不要) | 少ない (簡易簿記のみ・提出も最小限) |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 (簡易簿記) | 単式簿記( 簡易簿記) |
| 提出書類 | 確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書、第三表、第四表(該当時) | 確定申告書、青色申告決算書、損益計算書、第三表、第四表(該当時) | 確定申告書、収支内訳書、第三表(該当時) |
| 保存帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など | 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 法定帳簿・任意帳簿など |
| 保存期間 | 原則7年間(一部は5年) | 同左 | 原則5年間(インボイスありなら7年) |
| 特別控除額 | 最大65万円 (e-Taxや複式簿記の要件あり) | 10万円 | なし |
| 事前申請の有無 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 | 不要 |
| 赤字の繰越 | 最大3年繰越可能 | 不可 | 不可 |
| 経費の計上 | 減価償却・貸倒引当金など柔軟 | 一部制限あり | 制限あり |
| 事業専従者給与 | 全額経費にできる (事前届出が必要) | 制限あり (控除額に上限) | 制限あり (専従者控除) |
| 電子申告(e-Tax)の要件 | 65万円控除を受けるには必須 | 任意 | 任意 |
| 不動産所得の条件 | アパート10室以上または貸家5棟以上で65万円控除対象 | 一室からでも適用可能 | 控除制度なし |
確定申告をする際、多くの個人事業主やフリーランスが迷うのが
「青色申告」と「白色申告」のどちらを選ぶかという点です。
どちらも所得を税務署に申告する方法ですが、
- 控除の有無
- 記帳方法
- 提出書類
- 事前手続き
などに明確な違いがあります。
本記事では、「青色申告」と「白色申告」の違いを比較表や各項目ごとに詳しく解説し、
申告方法をわかりやすくご紹介します。
「青色申告」と「白色申告」の違い
「青色申告」と「白色申告」の違いは以下より詳細を説明いたします。
「節税効果」の違い ― 青色申告は圧倒的に優遇されている
節税という観点から見ると、「青色申告」は白色申告に比べて非常に優遇されています。
特に以下の点で差が出ます:
- 最大65万円の「青色申告特別控除」が適用できる(条件あり)
- 赤字の繰越(最大3年間)によって翌年以降の税金を軽減
- 配偶者や親族に対する給与を全額経費に計上可能(届出要)
一方、白色申告には特別控除や赤字繰越の制度はなく、節税効果はほとんど期待できません。
節税を重視する場合は、間違いなく青色申告が有利です。
「手続きの手間」の違い ― 白色申告は手軽、青色申告は帳簿・申請が必須
青色申告は、手続き面で白色申告より明らかに「手間」がかかります。
理由は以下の通り:
- 「青色申告承認申請書」の事前提出が必要(原則3月15日まで)
- 複式簿記の導入や詳細な帳簿作成・保存が求められる
- 控除を最大限に受けるには「e-Taxでの電子申告」も必須
一方、白色申告は単式簿記と簡単な収支内訳書だけで完結するため、
初心者や副業レベルの方には手軽な方法です。
帳簿や申請の手間を避けたい人には白色申告、
節税重視で将来を見据えるなら青色申告が向いています。
「事前手続き」の違い ― 青色申告には「申請書」の提出が必要
青色申告を選ぶ場合は、開始する年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
一方、白色申告は手続き不要で、申請をしなければ自動的に白色申告扱いになります。
「赤字の繰越・経費計上」の違い ― 青色は柔軟で有利
青色申告は赤字を3年間繰り越せるため、将来黒字化したときに節税効果が期待できます。
また、貸倒引当金や減価償却などの経費処理も幅広く認められています。
混同しやすい用語との違い ― 「年末調整」や「申告不要制度」との区別
| 用語 | 概要 |
| 年末調整 | 会社員が会社を通して税金を精算する仕組み (自営業者は対象外) |
| 申告不要制度 | 一定の収入以下の場合、確定申告が不要となる制度 |
| 青色・白色申告 | 個人事業主やフリーランスが行う確定申告の方法の違い |
「記帳方法」の違い ― 青色申告は「複式簿記」で精密に管理
複式簿記はお金の動きを詳細に記録する方法で、会計知識が必要ですが、
その分高額控除(65万円)を得ることができます。
白色申告や10万円控除の青色申告は、単式簿記で簡易に処理できます。
「提出書類・帳簿」の違い ― 青色申告は種類も量も多い
青色申告では、損益計算書・貸借対照表のほか、
必要に応じて第三表・第四表などを提出し、帳簿の保存義務もあります。
白色申告は収支内訳書が中心で簡易です。
「保存期間」の違い ― 青色は原則7年、白色は原則5年
青色申告では帳簿や書類を7年間保存する必要がありますが、条件により一部書類は5年で済みます。
白色申告でも法定帳簿は7年、その他は原則5年の保存義務があります。
「電子申告(e-Tax)」の要件 ― 最大控除を受けるには必須
青色申告で65万円控除を受けるには、
「e-Taxを利用する」または「優良な電子帳簿保存」が条件です。
10万円控除や白色申告ではe-Taxの利用は任意です。
「不動産所得の条件」の違い ― 規模によって控除の可否が分かれる
青色申告では、アパート10室以上または貸家5棟以上の規模があれば65万円控除が適用できます。
一方、10万円控除であればマンション1室からでも可能です。白色申告では控除制度はありません。
「青色申告」のメリットとデメリット
「青色申告」のメリット
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字の繰越ができる(3年)
- 減価償却や貸倒引当金などの経費処理が柔軟
- 家族への給与を全額経費にできる(要届出)
- 経営の実態を明確にできる(資金調達や補助金の審査でも有利)
「青色申告」のデメリット
- 複式簿記や詳細な帳簿作成など、手間がかかる
- 専門知識が必要になる場面も多い
- 事前の申請が必要
「白色申告」のメリットとデメリット
「白色申告」のメリット
- 手続きが簡単で、始めやすい
- 単式簿記で帳簿作成が容易
- 会計知識がなくても対応しやすい
「白色申告」のデメリット
- 控除がなく節税効果が小さい
- 赤字の繰越ができない
- 家族への給与も制限される
- 将来的に青色申告に切り替える場合、再準備が必要
まとめ ― 「青色申告」と「白色申告」の違いとメリット・デメリット
青色申告は、帳簿作成などの負担はあるものの、その分大きな節税メリットがあります。
一方、白色申告は簡単で導入しやすいものの、節税効果や経理機能の面で制約があります。
経理に対する自信の有無や、将来の事業規模を見据えながら、自分に合った申告方式を選びましょう。
特に、長期的に事業を継続する意志がある場合は、青色申告を視野に入れることをおすすめします。
| 比較項目 | 青色申告 (最大65万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
| 節税効果 | 最大65万円控除+赤字繰越・事業専従者給与など多彩な優遇措置あり | 控除は10万円だが、多少の節税は可能 | 控除なし・節税効果はほぼなし |
| 手続きの手間 | 多い (複式簿記・帳簿保存・申請書提出・e-Tax必須など) | やや多い (簡易簿記・一部帳簿・申請不要) | 少ない (簡易簿記のみ・提出も最小限) |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 (簡易簿記) | 単式簿記( 簡易簿記) |
| 提出書類 | 確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書、第三表、第四表(該当時) | 確定申告書、青色申告決算書、損益計算書、第三表、第四表(該当時) | 確定申告書、収支内訳書、第三表(該当時) |
| 保存帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など | 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 法定帳簿・任意帳簿など |
| 保存期間 | 原則7年間(一部は5年) | 同左 | 原則5年間(インボイスありなら7年) |
| 特別控除額 | 最大65万円 (e-Taxや複式簿記の要件あり) | 10万円 | なし |
| 事前申請の有無 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 | 不要 |
| 赤字の繰越 | 最大3年繰越可能 | 不可 | 不可 |
| 経費の計上 | 減価償却・貸倒引当金など柔軟 | 一部制限あり | 制限あり |
| 事業専従者給与 | 全額経費にできる (事前届出が必要) | 制限あり (控除額に上限) | 制限あり (専従者控除) |
| 電子申告(e-Tax)の要件 | 65万円控除を受けるには必須 | 任意 | 任意 |
| 不動産所得の条件 | アパート10室以上または貸家5棟以上で65万円控除対象 | 一室からでも適用可能 | 控除制度なし |